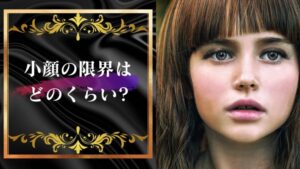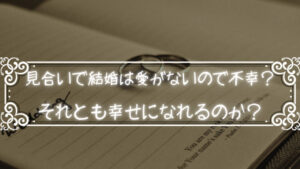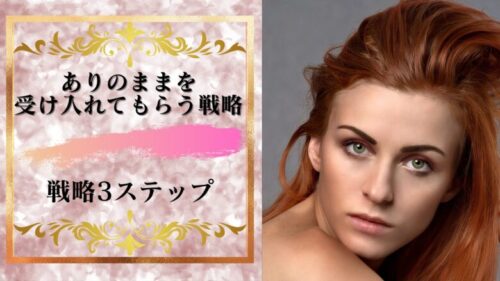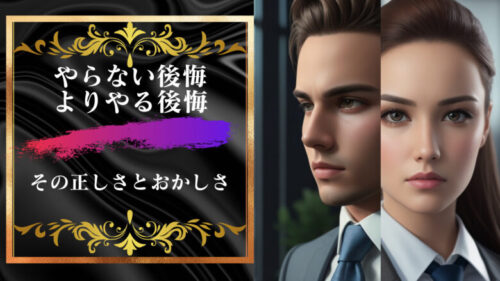人によっては「出世なんて仕事量や責任が増えるだけで大したうまみがない」と思うかもしれませんが、やはり出世した方が理不尽に怒こられる機会が減り比較的快適な気がしますよね?
それに中には「どんな手を使っても会社を自分のものにする」という野心を持っている人もいるはず。出世には「社内政治」、より具体的に言えば「根回し」が大事になってきます。
あなたの身の回りをみても、成果を上げていたからってだけで会社の幹部になった人って人は少ないはずです。出世したい人は仕事はもちろん社内政治もうまくやりましょう。
では、ゆるりとおおくりします。
目次
社長に人徳はいらない?
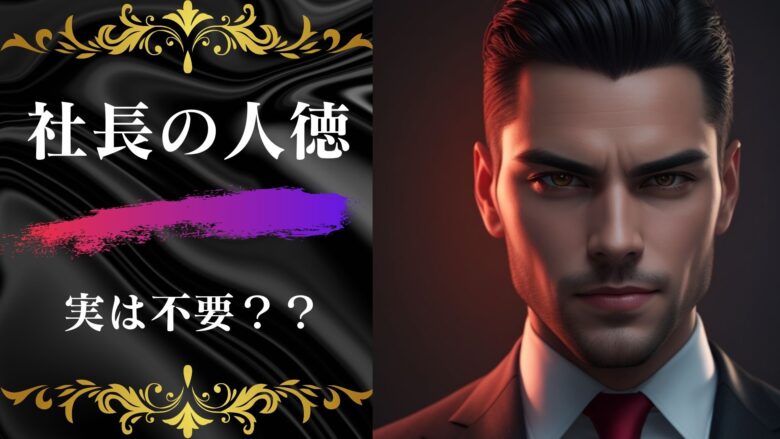


ちまたではいいリーダーの条件に人格者、つまり誠実であるとか思いやりがあるとかがよく上げられます。しかし、現実はそんな理想とはむしろ逆行しているのかもしれません。
組織行動学者のジェフリー=フェファーさんによるとアメリカでは悪いリーダーの方がいいリーダーより幅を利かせているとのこと。アメリカではリーダーシップ開発が熱心にそこかしこで行われているというのに、、、。
フェファーさんによるとこのような現象の理由として「集団の利益と個人の利害が一致しないこと」が挙げられるといいます。

そもそも、リーダーシップの理念の大前提は「組織と個人の利害の一致」であるといいますから、まあ土台から破綻しているってわけです。
個人単位でいえば自分自身の生き残りのためにリソースを確保しようと躍起になるが当然です。しかし、組織というものは多かれ少なかれ個人の犠牲の上に成り立っている側面は無視できません。
組織内で権力をもっているとなれば、真っ先に自分のリソース確保をしても何ら不思議はないわけです。まあ、組織と個人の利害は一致しないことの方が多いのよね。んー、むつかしいねえ。
現実は集団と個人の利益が一致しない事が多いため、リーダシップ理念の大前提は根底から崩れている場合が多い。
出世しようとすると美徳は悪徳になる?



さて、あくまでアメリカでの話ですがリーダーにはどんな性格をもっている人が多いのでしょうか?答えは以下!
- ナルシスト
- 状況により臨機応変に自分らしさを捨てられる
- 嘘つき(もちろん、嘘をつかない人もいる。でも少数派。)
- 思いやりよりも自己利益を追求する
なんか、一般に言われるリーダーの資質とは真逆の性質ですね。特に「謙虚であれ」ということを説く自己啓発系の人はいても、「ナルシストであれ」と説く人はあんまりいないですよね、多分。
確かにナルシストには「出しゃばり、目立ちたがり屋、自慢屋」のようなネガティブイメージが付きまといますし、実際のところイメージは悪いです。でも、これが出世という話になると状況は違ってくるといいます。
フェファーさんによるとリーダーの役割に関しては、実ははっきりしていない場合が多いそうです。このような場合においては、「確証バイアス」が効力を発揮するといいます。
確証バイアスとは自分の先入観や思い込みと一致する結果を探してしまう傾向のこと(血液占いなんかがその典型)。
いってみれば、「見たいものしか見ない、聞きたいものしか聞かない」という傾向です。
つまり、リーダーが強いカリスマ性を発揮して尊敬や信頼に値する有能な人間であるとの第一印象を与えてさえしまえば、その印象が長続きするということを意味しています。
くわえて、そもそも出世するためには縁の下の力持ちになっても基本的にずっと縁の下に居てはいけないんですね。
「ちゃんと自分はしっかりやっているぞ」と定期的に縁の下から顔を出してアピールしないことには存在にさえ気づいてもらえないって話です。このような点からすれば、ナルシストの方が有利なのも納得がいきます。

あと、一般にいわれる「経営者は人格者でないといけない」という話はそもそも成長途上の企業の社長には当てはまらない場合が多いんですね。
成長途上にある企業では生き残りをかけて結構グレーゾーンなやり取りをしていることも往々にしてあるもの。まさしく、「きれいごとなんて言ってたら即死する世界」。
あの経営の神とあがめられる松下幸之助さんですら企業黎明期はものすごくギラギラしていて、人格者とは程遠かったなんて話もありますしね。それは本田宗一郎さんも同じ(従業員にスパナ投げてくるとか冗談じゃないわな)。そこら辺については以下参照。
ただ、フェファーさんによると日本の場合はリーダーには名誉ある振る舞いが求められる傾向があるといいます。
とはいえ、わたしは原則として「日本ではモラルのある人格者のふりがより上手であることが求められる」が正解かなって気はしますが。
いいかたはわるいですが、「思いやり」がなくとも「あるように見せるのが上手ければ」人は本物だと思うものです。伝わらない思いはないのと同じであるというのと似ているかと。

組織のリーダーとして君臨するという観点からはいわゆる美徳も悪徳になるというか、「不利に働く」ということでしょう。
なので、日本の場合はアメリカ以上に「善人の振りした悪人(カバートアグレッション)が組織の長に上り詰める可能性が高い」と思われます。
まあ、組織の長になるのにキレイごとなんて言ってらんないってことですかね。なんか複雑な気分だわ。
出世競争や組織のリーダーとして君臨する観点からすると、いわゆる美徳は悪徳になる可能性がある。
リーダーなんて信用するな



もう、ここまで来ると「もう社長なんて、出世している奴らなんて信用できねえ!」と思うかもしれません。ええ、そうです。信頼しすぎてはいけません。信頼してもほどほどに疑いましょう。
特に出世競争で出し抜かれたり寝首を掻かれたことがある人は要注意!あと基本的に会社のためにどんなに尽くしてもあまり報われたりはしないと思ったほうがいいかもしれません。
もっとも、アメリカの事例をあげてどうこう言うのもあれですが、あの名うての起業家イーロンマスクさんですら普通に設立当初から秘書をやってくれていた女性に賃上げを打診されあっさり解雇しましたからね。

それにジョブズさんもサイコパスか?と思うくらいに理不尽なことでも有名でしたねえ、、。まじでロクな性格の奴がいねえ(笑)。それに会社にそもそも恩義を感じるっていうのも変な話です。
だって、従業員としては給料をもらって仕事しているので、もうそこで貸し借りなしで完結してるのですから。なので、恩義もクソもないです。ただ、リーダーが部下を思いやるようにする事も工夫次第では可能との事。
その決定的なものはリーダーが部下を思いやっているかどうかを測定しそれによってリーダーを評価する方法を導入することです。
リーダーに部下を思いやらせるためには、リーダーにとって部下を思いやることがメリットになる仕組みを作ることが重要。
例えば、ヒューレッドパッカード社では外部からCEOを連れてきて経営を行う以前には、直属の部下による評価がマネージャーの実績評価に取り入れられていたといいます。
このように「部下を思いやることが自分の利益にもなる状態」を作らないことには、リーダーは平然と部下の権利を踏みにじってくるってわけです。まあ、そりゃそうだろなって気はします。
そして、このようなリーダーの問題を根本的に解決するには、フェファーさんによるとリーダー育成のほかにリーダーに頼らないシステムの構築という手段があるとのこと。

つまり、リーダーが誰であってもうまく回る組織のシステムを作ろうって話です。これは個人的には政治なんかにも言える気がしますねえ。
なんつーか、人間が政治をやっても好き嫌いや派閥なんてものに拘泥してしまうのは歴史を見ても明らかなので、ここらで人間単独による統治をやめaiとかのように感情に左右されないものに統治機構の一部をになってもらったほうがいいきがしますな。
個人的に人間だけで政治をするのは無理な気がする。
社内政治を制するものが出世を制する



上述した通り出世していく人は基本的に「自己本位であって思いやりがない人である」と考えたほうがいいです。そして、日本の場合は思いやっている演技の上手い人ですな。
そうなると、社内政治をいかにうまくやるかを考えていかないと社内政治の犠牲者になってしまうでしょう。これはあなたが「出世する気がない」としてもです。
とはいっても、社内政治といわれても何をすればいいのかよくわからないと思います。そこで参考にしたいのが2010年のフロリダ大学州立大学の研究により提示された心理テストであるPolitical Skill Inventoryです。
この心理テストは実際の社内政治の能力と相関しているかを確認、調整して作られたものなんですね。なので、通常の心理テストより格段に信用できます。
この心理テストでは以下4つの点から社内政治のスキルを測定しているんですね。
- ネットワーク能力
- 対人影響力
- ソーシャルスキル
- (見た目の)誠実性
以下簡単に順次補足です。
・ネットワーク能力
ネットワーク能力とは端的に言うと、「人脈構築スキル」のことです。つまり、人と人の関係性をつないでいく能力のことを意味しています。
・対人影響力
対人影響力は自分の考えを人に伝えていく、自分の行動で他人の考えを変えていくのに役立ちます。
つまり、説得や交渉で大いに役立つ能力ということです。つまり、カリスマ性を身に着ける事が重要と言う事になりますね。
・ソーシャルスキル
ソーシャルスキルとは端的に言うと「感情を把握する能力」のことです。
この能力が低いと相手の立場でものを考えられなくなって無用なトラブルを発生させたりすることにもなるので、人間関係を構築する上では極めて重要な要素といえます。
・(見た目の)誠実性
上述したように、例えどんなにゲスであっても「誠実そうに見える」のが社内政治では大事になります。
そう、「真心より演技の方が大事になる」ということです。なんか、書いててやんなるけどね。
この見た目の誠実性に関しては、他人からの感情に影響されずに行動できる必要があると思われます。ここはサイコパスにならうべきところといえるでしょう。
戦略的根回しのすすめ



ここからは社内政治を考える上ではずせない要素である「根回し」について考えてまいりたいと思います。根回しは社内政治においては必須要素。前述の4要素でいえば、根回しはそのすべてを包括的に含む技術。
根回しをすることで新しいプロジェクトの立ち上げを成功させたり、イノベーションを起こせるようになるので根回しは出世以外にも非常に有効です。
ちなみに、根回しは英語で「ステルスストーミング」といいます。以下、根回しのことはステルスストーミングの呼称で統一しますね。ステルスストーミングは以下の3要素からなります。
ステルススポンサー
ステルステスト
ステルスリソーシング
以下順次解説します。
・ステルススポンサー
ステルススポンサーは自分の身近にいる上司やメンバーと協力関係を構築することです。そのためには相手にアドバイスを求めましょう(アドバイスシーキングという)。
最終決定権者にいきなり相談やら提案やらをしてしまうと、利害の対立する人につぶされたり妨害されたりしかねません。ある程度協力者が増え、実行直前になるまで計画が明るみになっては困ります。
また、事前に話をふられなかった上司としても自分がのけ者にされたようで気分が悪いものです。なので、人によってはバカバカしいとも思うでしょうが、上司やメンバーのメンツを立ててあげましょう。
これが遠回りにみえて近道ですね。
・ステルステスト
ステルステストとは簡単なプロトタイプ、試作品等を作って提示することです。試作品、プロトタイプを提示するとイメージをしやすくなり、あなたに協力してくれやすくなります。
イメージできないと人は口では協力するよといいつつも、実際には手を貸してくれないものです。新しいプロジェクト等を立ち上げるなら、なるべくイメージしやすい試作品を用意してみてください。
・ステルスリソーシング
ステルスリソーシングとは相手に協力を求める代わりに相手の仕事にも協力するということです。 端的に言うと、相互互恵関係を目指すわけですね。とはいえ、実際にそこまで労力がかかることはないです。
大方の場合、上述したように相手にアドバイスを求めつつ「私にもあなたの仕事を手伝わせてください」等と協力する意思表示をしておきましょう。
実際にあなたが協力することになったとしても、それはそれで相手に貸しを作れるので、その後あなたは相手に快く協力してもらえるでしょう。
組織の現実と理想は全く違う?



さて、最後に理不尽な会社組織というものに対する向き合い方を「悪いヤツほど出世する」から6つ見てみましょう。
他人の言葉を信じるのではなく、リーダーの実績と行動をよく見る
リーダーの「あるべき姿」と「現実の姿」を混同しない
普遍的な助言を求めない
白か黒かのように考えない(現実世界に勧善懲悪はない)
許しても忘れない
時には悪いこともしなければならないと心得ておく(多分これが普通の人には結構きつい!)
さて、これらについて詳しくは本書を読んでみてくださいな。具体的に何をしたらいいかわかるでしょう、、、、。
ちなみに、昨今はクリエイティブ性が重視される風潮があるとされていますが、これは大企業の場合は例外です。クリエイティブな人は大企業だと、いくら有能でも疎まれて出世できない可能性があります。
なので、クリエイティビティが高い人は、出世を考えるのならあくまでも組織の慣例に従った方が賢明かと思います。なかなか、出世って難しいものですねえ、、、。
まとめ:社内政治の勝者こそが出世を制する

この記事では「社内政治で勝ち上がるにはどうするか」と題してお送りしました。なんか、今回は始終人間不信をあおるような展開になってしまってもうしわけありません。
とはいえ、個人的には現代の組織の日本のリーダーの大半もアメリカほどではないにせよ上述したような傾向を持っていると思います。
なので、彼ら彼女らを信頼しすぎることなくほどほどに疑いながら、表向きは誠実に振舞うことが大事。
とりあえず、出世したいなら表向きの誠実さを大事にしつつ上手い事根回しをやって競争相手を打ち負かして組織の長の座を取りに行きましょう。
以上!