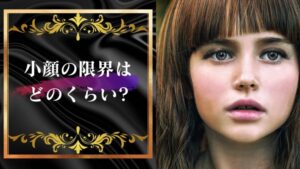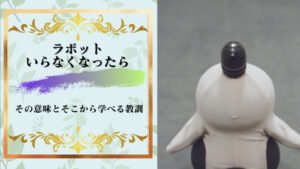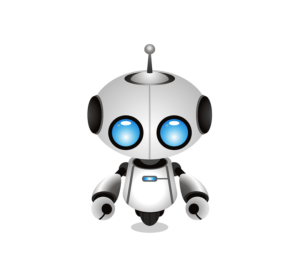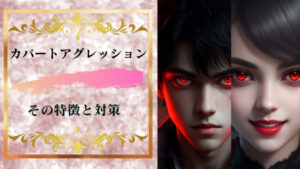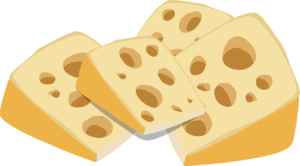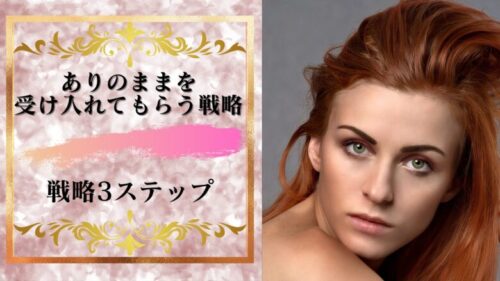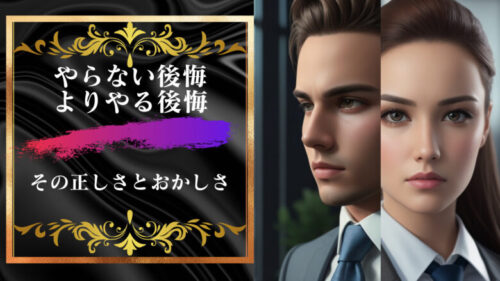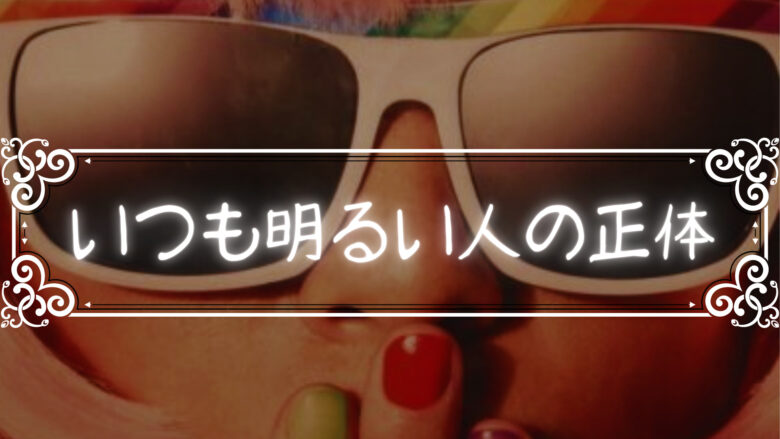
今回は以下の様な方にむけておおくりします。
・いつも明るい人が何を考えているのかわかんなくて戸惑っている人
・人前で明るくいることに疲れてしまった人

脱マンネリストで心理カウンセラーのオニギリです!
今回もよろしゅう!!今回の話題は「いつも明るい人は実はものすごく闇の深い人かも?見た目じゃわからない深い闇。」と言う話題です。
あなたの身の回りにもいませんか?
いっつもいっつも笑顔でやたらテンション高めの太陽みたいな人。
もしかしたら、そういう人も心に深い闇を抱えているのかもしれません。
というのも、明るい人にもいろんな種類があるのです。
その種類というのが以下のパターン。
- 深い闇を持つが社交的にふるまっている人
- ただ単に明るい人
- 明るさを誇示する人
もし、あなたがいっつも無理して明るくしている人であるなら、聞いてほしい。もう無理せずに自分に素直生きた方がいいです。無理をするとめっちゃ疲れるので。
今回はいつも明るい人の心理を解き明かしていきたいと思います。
この記事で、「いつも明るい人」を不思議に思っている人は疑問氷解、「いつも無理して明るくしている人」はもっと自然体に、そんな感じになったらいいなあと思います。
では、ゆるりとおおくりします。
目次
「いつも明るい人」なんてどう考えてもおかしい
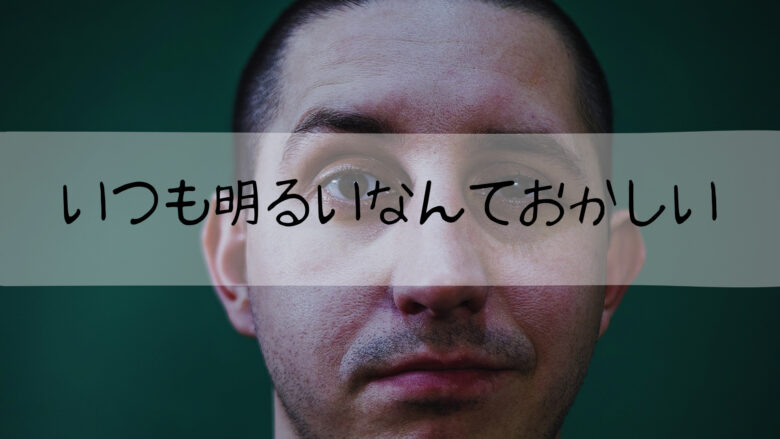
一般的に、明るいことはいいこととされていますし、「原則としていい事」です。
というのも、心理学的には「外向性」は人から好かれるための重要な要因であると言われていますから。ただ、これは主に「他人に好感を持たれるかどうか」という意味での「いい事」にすぎません。
もし、もともと内向的で本質的な意味でそこまで明るくない人が、「他人に好かれるために無理をして明るくする」としたらどうでしょうか?
この場合は、必ずしも「明るい事がいい事である」とはいえません。
自分の本質を偽って外向的にふるまうと、内向的な人はかなり疲れてしまうのです。そんな無理をずっと続けるなんて拷問もいいところ。
先ほど「原則」と言ったのはこのような例外があるためです。それに、そもそも論ですが、人間は気分の浮き沈みはあって当然なんですね。これは外向的な人でも同じです。
気分がいつでも一定して明るい、、、、それは人間ではなないでしょうね。AIですかね?
なので、「常に明るい必要なんてない」んです。
そもそもそんな事が人間には無理なんですから。それと対人関係においても、明るいことはいいことばかりではありません。
例えば、精神的に疲れ切っている人に対して明るさはある意味で禁忌ともいえる代物。というのも、明るさを受け取るのにも精神力が必要だから。
もしあなたが、完全に落胆しきっているときにものすごく明るく接して来られたらどうでしょう?
きっと、大抵の人はなんとか力を振り絞って相手の明るさや笑顔に応えようとするでしょう。応える方は実は我慢していることも多いんですね。
- 精神的に参っている人にとっては明るさはきつい場合が多い。明るさを受け取るには体力が必要
ただ、こんなことをいうと
「いやいや、落ち込んでいる時こそ明るくしてほしいよ。しんみりした感じで来られちゃ気が沈む」
なんていう人がいるかもしれませんね。
実は、私もこのタイプです。
「暗い時ほどわらっていようz!」
「ピンチの時ほどジョークをとばせ!」
て感じです。
しかしね、そんな人ばかりではないので、「疲弊している人に明るく接する」のはリスクがつきもの。
で、私なりに考えた結果、このような反応の違いが出るのは、もしかしたら「外向性か内向性か」で外界の刺激に対する感じ方が違うからかもしれません。
外向性は人との交流でエネルギーをためます。一方で、内向性の人は一人の時間を確保することでエネルギーをためます。
もし、内向的な人が落ち込んでいる時に無駄に明るく接したら大変ですね。内向的な人はますます疲へいしてしまいます。
一方で、外向性が高めな人なら明るく接してもらった方が気が安らぐでしょう。ですから、「いつでも誰にでも明るく接する」のは正しいとは言えないんです。
そして、「常に明るいなんて異常」なんです。
- 人は感情に波があって当たり前。常に明るくいようとする必要はなし!
いつも明るい人の分類
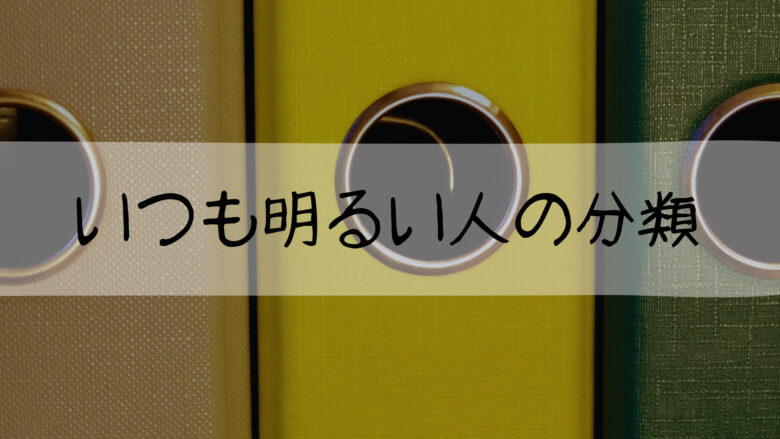
さて、「いつも明るい人のおかしさは異常」と言ってみたところで、現に「常に明るい人」はいるんですから謎は深まりますよね。
「いいや、あれは人間ちゃう。人間に化けた火星人や!」とかいうわけにもいかないので、原因を探っていきましょうか。
個人的に明るい人には以下の三分類があると思っている次第。
- 深い闇を持つが社交的にふるまっている人
- ただ単に明るい人
- 明るさを誇示する人
以下順次補足です。
・深い闇を持つが社交的にふるまっている人
体感上このタイプが一番多い気がします。
表面上はとても明るくて親切なのに実は心に深い闇を抱えているという人です。
深い闇の原因はいろいろあるとしても、「いつも明るく親切である」ということが相手の機嫌を取ろうとする行為であると考えた場合には「深い闇の正体」は特定できます。
それは月並みでありますが「自尊心の低さ」でしょうね。
自分のあるがままを認めることができないと
「私は明るくしていないと嫌われてしまう。だから、いつも明るく親切でいなきゃいけないんだ」
と考えてしまいます。
あんまり、事態が悪化すると
「明るくない私なんて価値が無いんだ!」
なんて考え始めてしまうでしょう。
このような傾向は幼少期に複雑な家庭環境で育った人に多い気がします。いずれにせよ、無理に無理を重ねている状態と考えて間違いありません。本人はかなりつらいはずです。
- 明るい事が存在意義になるとしんどい。
もし、誰かに嫌われることを恐れているならこちらを、自尊心を高めるならこちらを見てみてくださいなもう、無理しなくていいっす!
そして、やや専門的な話をしますと、いつもやたらと明るい人の中には幼少期の不適切な養育により愛着障害をわずらっている人もいます。
具体的にはいうと、家庭環境が複雑だった人の中には、外に人間関係を求めるため社交的になりその結果明るく見えるようになった人もいますね。
・ただ単に明るい人
中には、ただ単に明るい人というのがいます。
つまり、「明るいのは元々の性格」なんです。
多分、このタイプの明るい人は日本人には少ないと思います。
このタイプの人は(私も多分そうですが)不安を感じにくい遺伝的素質を持っている可能性があるんじゃないかと思います。具体的にいうなら「セロトニントランスポーター遺伝子」の働きの強さです。
セロトニンとはメンタルの安定に大きく寄与する神経伝達物質です。別名を幸せホルモンなんて言ったりもします。セロトニントランスポーター遺伝子とはセロトニンの伝達に関する遺伝情報が書き込まれた遺伝子です。
まあ、あまり詳しく説明すると本旨からずれるので省略しますが、日本人のセロトニントランスポーター遺伝子の働きは概して弱いです。ですから、日本人は不安や恐怖を感じやすい人が多いと言えます。
- セロトニントランスポーター遺伝子の働きが、外交性の度合いと関係している可能性はある。
しかし、日本人の3%ほどはセロトニントランスポーター遺伝子の働きが強いのです。
この3%の人はきっといつも明るい人に含まれるのではないでしょうか。まあ、可能性ですがね(笑)。ちなみに、私は遺伝子検査をしていないので分かりません。
・明るさを誇示する人
実はこのタイプは明るい風を装った陰湿な人です。ハッキリ言いましょう。
このタイプは「さも明るく見せかけて闇をふりまくもの」です。
このタイプの人々は明るくすることで何をしようとしているかというと「マウンティング」、つまり自分の支配力を見せつけることが狙いです。このタイプの人には大方2種類います。
それが以下です。
・明るいことをステータスだと思っているタイプ
このタイプはいわゆる「自称陽キャ」です。
静かな人をみつけて「あいつインキャじゃね?」なんて人に簡単にレッテルを張る迷惑な存在です。
きっと、学生時代に迷惑を被った人は多いんじゃないでしょうか?
なお、このタイプも自尊心低いでしょうねえ。
人を攻撃することで自分の自尊心を補おうとしているんですから。
- 自称陽キャは、自尊心低めかもしれない。
ただ、中には「人を苦しめること自体が快感だ」というサディズム傾向を持っている者もいるので注意が必要です。
・明るくすることで人気を得て、場を支配しようとするタイプ
このタイプはまあなんというか「論外」です。
関わるととても有害です。
いい人のふりをしている悪いヤツなんですよ。
表向き思いやりのあることを言っているかと思えば、うらでは人の陰口を拡散していたりするやつです。
このタイプの人を心理学では「カバートアグレッション」と言います。カバートアグレッションには対処法があります。
カバートアグレッションへの対処法についてはこちら。
- 場の支配を目的として、戦略的に明るくふるまっている奴はカバートアグレッションの可能性あるかも。
明るさより心の温度と距離感
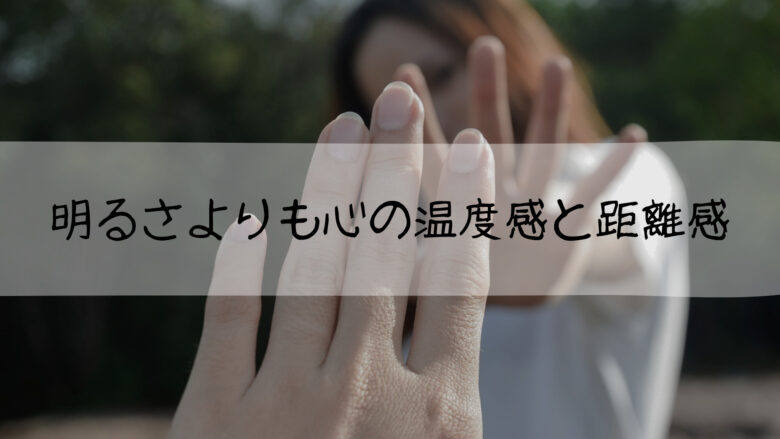
明るいことがいいのは、「原則」でした。
いつも明るいなんて通常は「明るくする方にとっても」、「その明るさを受け取る方にとっても」辛いものです。
どちらも、無理せざるをえないんですからね。誰も幸せになってません。
まあ、いつも明るくてありがたいのは「一部の外向性が極度に高めの人」だけです。生物学的には内向性の人口はおよそ総人口の1/3と言われています。
ということは、総人口のうち残り2/3外向型か内向と外向の中間の両向型ということになります。ですが、外向型や両向型にも外交の度合いというものがあります。
- 日本人は、1/3 が内向型で残り2/3が外向型と両向型。
きっと、外向度の低い外向型や両向型の人は落ち込んでいたら、明るくなんてこられたくないと思いますね。上述しましたが、「明るさを受け取るのも精神力が必要」です。
だから、「明るくいる」ことなんかをめざすんじゃなくてもっと「心の距離感」や「心の温度」を大事にしませんか?と言う事ですね。
相手の心との適切な距離を取り、相手のテンションと同じくらいのテンションで接するんです。相手に負担にならず、自分も負担にならない接し方がいいんです。そうやって接してくれる人は一緒にいて気分がいいはず。
本当の意味で明るい人は無理をしません。本当の明るさは人口的な蛍光灯のような明るさではなく、空にある太陽みたいなもんです。
太陽は空の雲ゆき次第では隠れてしまいます。でも、かならずいつか顔を出します。そして、顔を出したら出したで明るくあたたかく地上を照らします。本当の明るさってそんなもんかなって感じです。
自然に、感じるがままに明るくいましょうってことですな。
- セロトニントランスポーター遺伝子の働きが、外交性の度合いと関係している可能性はある。
おわりに
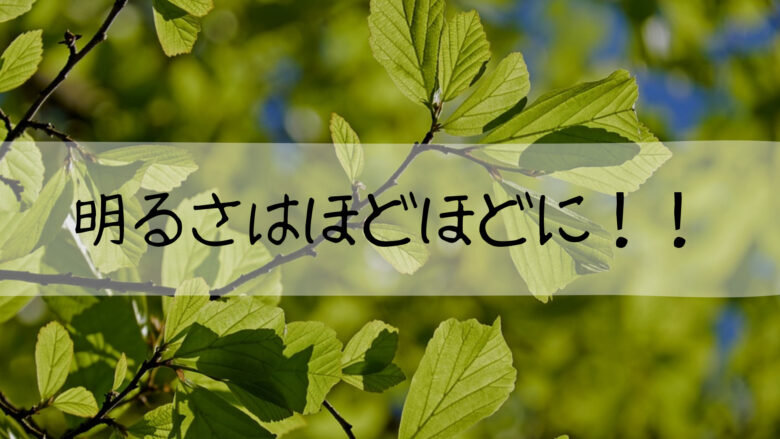
この記事は「いつも明るい人は実はものすごく闇の深い人かも?見た目じゃわからない深い闇」と題しておおくりしました。
人間は「何時でも誰にでも明るくいる」なんて無理なんです。
確かに人の目が気なる気持ちも分かりますが、もっと自分の気持ちに素直に生きてもいいと思います。
自分を偽るということは「本当の自分の気持ちを否定すること」です。もっと、自分に優しくすると気楽に生きられますよ。あまり無理しないようしたいもの。
なお、心の支えが欲しい人はペットを飼ってみるのも手かもしれませんね。ペットを飼うことで癒し効果が得られるといいますから。
ペットを飼うことに抵抗があるとか賃貸で買うことができないという人は、ペットの代わりにロボットを買うのもありでしょう。特に、家族型ロボットのラボットには、さながら生きているかのような生命感があり大分癒されます。
では!
参考記事等
中二心がうずくかっこいい暗い曲23選。さあ、闇に浸れよ、、、、。
さびしがり屋のミミッキュにみる現代の闇。もはや、他人事ではないかもよ?
バンギャはメンヘラなのか?本当に性格がヤバいのか?考察してみた。
演歌好きの人の心理や性格を考察してみた「なぜ演歌が好きなんだ?」