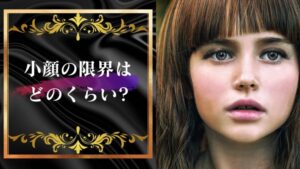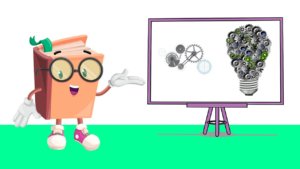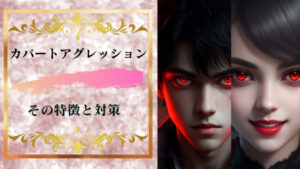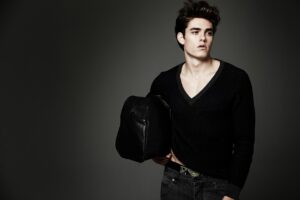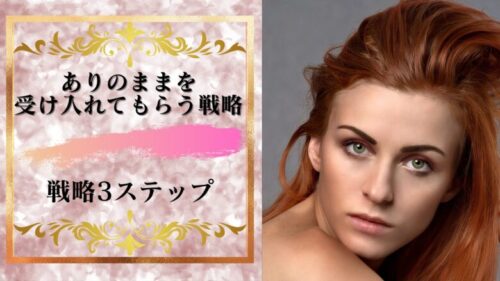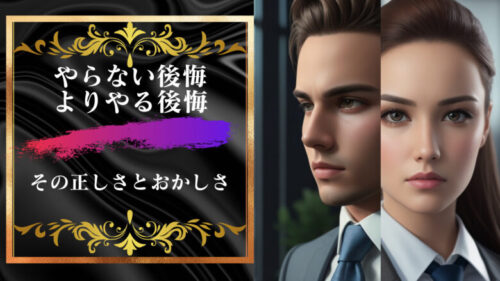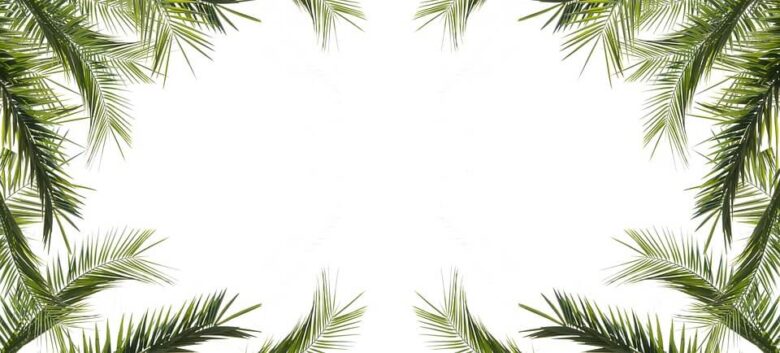
「最近、本当に人間の言語行動って不思議だなあって思ってきた。人は言語を使ってどうやって世界を認識し捉えているんだろうか、、、。」
んー、深すぎて人生かけても答えが出そうにない疑問だわ、それ。
オニギリス!
脱マンネリストで心理カウンセラーのおにぎりです。
今回もよろしゅう!!
今回の話題は「「関係フレーム理論」をなるべく分かりやすくかみ砕いて説明してみたい」という話です。
今回は以下のような方に向けておおくりします。
- 関係フレーム理論ってなんぞ?って思っている人
- 人間の言語や概念についての学習がどのように進むのか気になっている人
さて、こんなマニアックな記事へようこそ!!
多分、「関係フレーム理論 わかりやすく」とかいうキーワードで検索していらっしゃったのではないですか?
てことは、おそらく大学とかで心理学を履修されている方や何らかの縁で、心理学の割とガチなところまで学んでいらっしゃるお志高い聡明な方々ばかりがお集まりのことだと思います。
ええ、そうでもないと、「関係フレーム理論」なんて言葉に出会うこと自体ないですからね。
普通に生きていたら、こんな専門用語を知ることはないです。
まあ、今回はわたしなりに全力で「なるべくわかりやすく」関係フレーム理論を解体していくんで何卒よろしゅう!!
「おまいじゃあ信用ならねえよ」とか「もっと、詳しくはなさんかい!!どあほ!!」という方は今回の参考文献等を各自ご確認くださいませませ。
今回は熊野宏昭さん著「新世代の認知行動療法」を主な参考にしています。
なお、本記事をお読みいただく前に、「言葉と自由意志の関係」についての記事を読んでおくと理解が深まるかもしれません。
しらんけど。
では、ゆるりとおおくりします。
目次
関係フレーム理論とは一体なんだいな?
早速ですが、関係フレーム理論とは何でしょうか?
一言で言うと、関係フレーム理論とは
「関係フレーム付けを用いた人間特有の学習システム」
のことです。
んー、なんて意味の分からない、、、。
はい、気を取り直してまいりましょう。
関係フレーム理論(以下RFTという)を理解するにあたっては、どうも「関係フレーム付け」というものを理解する必要があるようですね。
精神科医のニコラス=トールネケさんによると、関係フレームづけとは、
「恣意的に適応可能な関係反応」
だそうな。
、、、、、うん、全然人に伝えようって気が感じられない定義ですわ。
より詳細に言うと、ここでいう関係反応とは「刺激同士の関係反応」のこと。
刺激同士の関係には実に様々なものがあり、例えば以下のようなものがあります。
- 等価
- 比較
- 反対
- 階層
- 因果
- 空間の位置関係
- 時間の関係
、、、などなど
そして、それぞれの刺激を関係づける汎化オペラントは幼少時における「多数の範例による訓練」によって学習されるとされております。
※オペラントとはスキナーが「「operate(動作する)」」から作った造語。特にこれ単独で意味があると解さなくてよいと思う。
※汎化とは、初めに条件づけされた刺激や条件以外の類似した別の刺激や条件でも反応や学習効果を生じさせること。例:「子供が『柴犬』にかまれて痛くて泣いた」→「『犬』をみたら子供がなくようになった」。
そして、「恣意的に適用可能」とありましたが、この「恣意的」という記述を理解するにあたっては、「モノと名前の関係」を考えるとわかりやすいです。
例えば、為政者などが法律で「じゃあ、今から『これまで猫と呼ばれてきた動物』をボビーって呼ぼうぜ」と決めたら、「動物の猫」と「ボビー」という名前の間には等価関係が生じることになります。
この際、そもそも「なんで猫をボビーって呼ぶことになったのか?」と考えれば、それは発話者の単なる思い付きとかボビーオロゴンが好きだとかそんな私的すぎる理由かもしれません。
そう、猫をボビーと呼び始めるのは「恣意的」、つまり「論理的な必然性なんて微塵もない行為」なんですよね。
あと、もう一つ例を挙げておきましょう。
例えば、10円玉の方が硬貨としては100円玉よりもサイズが大きいですが、価値は100円玉の方が高いです。
でも、こういった価値の差は「日本政府や日銀等が勝手に決めただけ」ですよね?
全く日本の文化をしらないアフリカの人等からしたら、ひょっとしたら10円玉の方が高価だと勘違いしてしまうかもしれません。
このように刺激間の関係というものは「恣意的に適用することができる」のです。
ということで、最後にもう一度トールネケさんによるRFTの定義を補足しておさらいしておくと、
「RFTとは『論理的必然性なく適用することができる刺激と刺激の間の関係反応である」
という事になると思います。
んー、それでもわかりにくいわ、、、、。
関係フレーム理論における言語行動の定義
そもそも、このRFTは行動分析学の土壌に育ってきた概念です。
そして行動分析学は、スキナーさんの「行動の制御変数を環境に求める」という一貫した考えのもと創始された研究体系になります。
スキナーさんは言語行動を独自に定義したり、その機能や特質等の観点から5つに大別したりしました。
スキナーさんが定義した言語行動についての詳細は以下の記事からどうぞ。
しかし、スキナーさんは「言語行動という概念を「発話者に限定したいた」という事もあってか、彼の概念だけでは説明のつかない行動や事例というものも存在していました。
それを補完し、より発展させるべく登場してきたのがRFTであると解釈できるかと思います。
そして、RFTでは言語行動というものを以下のように定義しているそうです。
「出来事または刺激を、3つの基準(相互的内包、複合的相互的内包、刺激機能の変容)に従って、関係フレームづけること」
熊野宏昭著「新世代の認知行動療法」p171より引用
、、、、うん、ダメだなこりゃ(笑)。
意味が分からん!!
という事で、相互的内包、複合的相互的内包、刺激機能の変容のそれぞれについて以下見ていきましょう。
相互的内包
例えば、ここに以下のような「A B C」という3つの文字があるとしましょう。
A
B C
ここで「A→B」、「B→C」という関係を学習すると、それと同時に「B→A」、「C→B」という関係も理解できるようになります。
このように「A→B」を学習すると「B→A」が理解できるようになることを「刺激等価性がある」といい、このような実際には学習していないはずの関係を理解できるようになることをRFTでは「相互的内包」といいますね。
なお、このような学習は動物には起こらないといわれている模様。
複合的相互的内包
上記A B Cの文字において、「B→A」と「A→C」等関係を学習すると「B→C」と「C→B」という関係も学習されます。
このような派生的な関係の学習を複合的相互的内包というんですな。
名前はごついけど指している事象はそんなに面倒な事ではありませんね。
刺激機能の変換
最後に刺激機能の変換についてです。
これはそこまでめんどくさいものではありません。
例えば、実物の犬を見た子供が「い、ぬ」と呼ぶことを覚えたとしたら、「い、ぬ」という二つの音が実物の犬が持つ機能を持つことになります。
つまり、ここでは最初は「いぬ」といわれても何のことかわからなかった子供が「いぬ」という音と「実物の犬」の対応関係を学習したことで、「いぬ」といわれると「実物の犬を想像できる」ようになっているんですね。
これを刺激の変換と言います。
結局、関係フレーム理論なんて何の役に立つんだい?
上述したのですが、RFTの登場によってスキナーさんの理論では説明のできない事象に対して説明がつくようになりました。
例えば、スキナーさんの理屈で行くと「ある人が誰かに頼まれたのでものをとってあげた」という事象は言語行動には当たりません。
これはスキナーさんが「言語行動という概念を発話者に限定していた」が故です。
また、「自分が自分に対して語りける」なんて場合に「自分は発話者であると同時に聞き手でもある」と解釈することが可能となりました。
RFTによって、言語行動の対象にこれまでの「発話者」に加えて「聞き手」も加わったのは多大なる理論上の進歩です。
まあ、スキナーさんは言葉が生まれる前の定義について主に取り扱っている一方で、RFTは言葉が生まれて以後の話を主に取り扱っていると考えてもいいでしょう。
このRFTの登場によって、認知行動療法に新しい地平が開けたといえます。
おわりに
今回の記事は「「関係フレーム理論」をなるべく分かりやすくかみ砕いて説明してみたい」と題しておおくりしました。
今回はできる限り全力で関係フレーム理論について解説してみたつもりであります。
まあ、とはいえ、色々とはしょっている気もするので、参考文献等を各自で読み込んでくれるともっともっと理解が進むと思いますねえ。
心理学って奥が深いのお、、、。
では!
参考記事等
失うものがない強さと大事なものを守るための強さはどちらが強いか?
疲れて何もやる気が出ないならいっそ何にもしない時間を作ってみよう
「これから猫飼いたい人必見」飼いやすい猫にはどんな猫がいる?
参考文献等
熊野宏昭著「新世代の認知行動療法」
ニコラス=トールネケ著「関係フレーム理論(RFT)をまなぶ 言語行動理論・ACT入門」