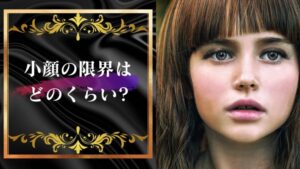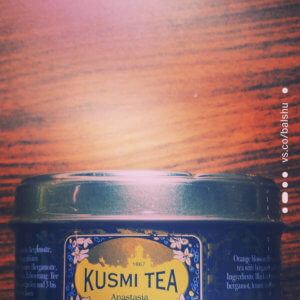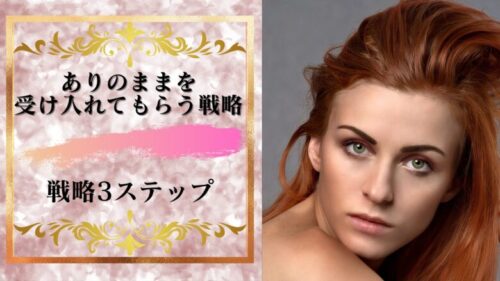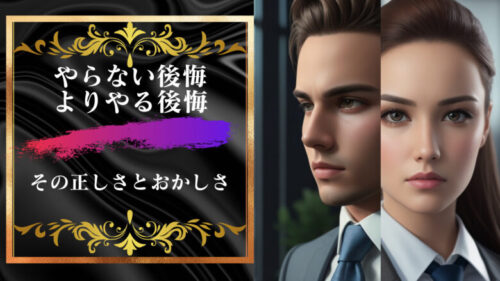「緑茶っておいしいよね。しかも飲んでいるとホッとする気がするわ。特にメンタルが落ちているときに緑茶飲むと気持ちが落ち着くし、次の日元気にやっていける気がする。でも、実際に緑茶にはメンタルを安定させる効果があるっぽいね。」
うん、そうね、同感だわ。
緑茶っていいよねえ、紅茶もおいしいけど。
特に疲れているときに飲む緑茶は最高よね。
オニギリス!
脱マンネリストのオニギリです!
今回もよろしゅう!!
今回の話題は「緑茶はメンタルにいいし、ウツ病予防になるかもしれない」という話です。
はい、緑茶にはメンタルにいいといわれていますし、わたし自身の実感としてもそうであると感じています。
そもそもわたしは紅茶、特にアールグレイマニアなんですが、緑茶にもめちゃめちゃ目がないです。
お茶ってストレス解消にはもってこいの飲み物なんですよ。
そこで、今回は緑茶のすばらしさを全力でお伝えしてみたいなって思います。
メンタルを落ち着けたい人やウツ病を予防したい人は是非とも日常生活に緑茶を取り入れてみてはいかがでしょうか?
では、ゆるりとおおくりします。
目次
緑茶とは?

お茶とはツバキ科の植物であり、中国では漢の時代から解毒用として珍重されていいたといいます。
そして、お茶は後に飲用に発展し、生活必需品となって人々の生活に浸透するようになったそうです。
日本では僧侶の永忠さんが805年に、留学していた唐から薬として持ち帰ったことが最初であるといわれています。
お茶は非常に歴史ロマンにあふれる飲料なんですねえ。
なんか、感慨深い!
参考
で、飲料としてのお茶の種類には紅茶、緑茶、ウーロン茶、プーアル茶、、、、いろいろなものがあります。
そして、緑茶とは日本茶の一種です。
なお、日本茶には他にもほうじ茶や抹茶等もありますね。
緑茶は茶葉を発酵させずに作ったお茶のことを言います。
実は知らない人も多い気がしますが、茶葉は半分発酵させるとウーロン茶になり、しっかり発酵させることで紅茶になるんですねえ。
そう、紅茶も緑茶も茶葉自体は同じでその発酵度合いが違うだけだったんです。
意外でしょ?
また、緑茶を焙煎するとほうじ茶になり、玄米を加えると玄米茶になります。
参考記事等
緑茶の種類には何がある?

緑茶と一言で言っても、実はですね、いろーんなお茶があります。
中には「緑色っぽければ緑茶じゃね?」とかいう人もいるかもしれませんが、現実はそう甘くなのですよ(←貴様何様)。
緑茶には以下のようなバリエーションがあります。
- 玉露
- 煎茶
- 番茶
- 抹茶
- ほうじ茶
- かぶせ茶
以下順次簡単に解説を付してみます。
・玉露
新芽が2~3枚開き始めたら日の光をさえぎって育てるという被覆栽培によって育てたお茶です。
なお、被覆栽培とは新芽の生育に茶園を遮光資材で被覆して、一定期間光を遮って育てる方法のことをいうんですね。
そして、被覆栽培には実に400年程の歴史があるとか。
被覆栽培について詳しくはこちらからどうぞ。
参考
http://www.pref.kyoto.jp/chaken/mame_shade.html
被覆栽培により日光ををさえぎって茶葉を育てることで葉の光合成が起こらないため、渋み成分であるカテキンの合成が抑制される一方でうまみ成分であるテアニンの含有比率が増加します。
なので、玉露は他の緑茶に比べてより渋みがなく、旨味が豊富な味わいに仕上がるというわけです。
・煎茶
煎茶は遮光しないで育てたお茶です。
そのため、程よい渋みとすっきりとした味わいに仕上がります。
なお、日本の流通量の80%以上を占めるお茶でもありますね。
・番茶
番茶は正直定義が難解です。
ただ、一般には「煎茶の安いもの」とか「下級のお茶」なんて認識が一般的でしょう。
しかし、これではざっくりしすぎてなんか釈然としません。
以下のサイトでは番茶の条件として以下の3点を挙げています。
1.柔らかな新芽でなく、硬化が進んだ茶葉(コワ葉という)を原料としたお茶
2.一度収穫した後、遅れて伸びた茶葉(遅れ芽)を原料としたお茶
3.仕上げ時に選別された大型の茶葉を原料としたお茶引用
いずれにせよ、廉価という点では変わりませんが、かなり具体的ですよね。
また、番茶は一般に含有成分が少ないという印象があり、お年寄りや子供にはマイルドな味わいで適しているなんて言いますね。
そして、番茶としては徳島の阿波番茶や京都の京番茶、愛知県足助町の足助寒茶などが有名だったりします。
ちなみに、茶業界で使われる「一番茶、二番茶」等といった呼び名は「収穫時期による分類」であって、いわゆる番茶とは無関係です。
なお、収穫時期については以下のようになっているとのこと(静岡の場合)。
- 4月~5月にかけて摘採製造:1番茶
- 6月に摘採製造:2番茶
- 7月~8月にかけて摘採製造:3番茶
- 9月~10月にかけて摘採製造:4番茶
・抹茶
抹茶はてん茶を石臼でひいたもののことを言います。
では、てん茶とは何なのかというと端的に言うと「玉露と同様に被覆栽培により育てたお茶」です。
なお、製茶の工程で生葉をもまずにまず「散茶」という工程を経るのがてん茶と玉露との決定的違いになるとのこと。
※まず散茶をするのはてん茶の方
詳しくは以下からどうぞ。
参考
http://www.tokyo-cha.or.jp/entry2013/20130607_1803.html
あ、そうそう、ここでいう「てん茶」は漢字で書くと「甜茶」ではなく「碾茶」ですからね(碾は『臼でひく、ひく』等の意)。
甜茶は中国茶の一種で別物です。
誤解なきよう。
・ほうじ茶
ほうじ茶は煎茶や番茶、茎茶等を強火でほうじて製造したお茶のことをいいます。
高温で焙煎しているので、アミノ酸やカテキン、ビタミン、カフェイン等の含有量が少ないお茶になるんですね。
まあ、あれです。
熱が加えられると栄養素って壊れますからね。
野菜も生で食べたほうがいいというのもこれが主な理由といえるでしょう。
味の特徴としては香ばしくさっぱりしています。
脂っこい食事のあとだったり、ねる前に飲むのはとってもおすすめですね。
参考記事等
・かぶせ茶
かぶせ茶とは玉露と煎茶の中間に位置するお茶です。
玉露や碾茶が少なくとも20日間以上日光を遮るの対して、かぶせ茶は7~10日間程度とその遮光時間は短くなるといいます。
味については煎茶よりも風味が穏やか、かつ玉露のように強いうま味や甘味はないので、苦みや渋みが苦手な人にはおすすめでしょう。
参考
https://www.tokichi.jp/tea/tea_kabuse.html
お茶に含まれる栄養素

さて、ここからはお茶に含まれる栄養素について見ていきましょう。
なお、お茶に含まれている成分には「水溶性」と「不溶性」のものがあります。
以下、含有成分を水溶性と不溶性に分けて示してみましょう。
・『水溶性成分20~30%』
- カテキン類:抗酸化、抗ウィルス
- カフェイン:強心、眠気防止
- テアニン:リラックス効果
- ビタミンC:抗酸化、風邪予防
- ギャバ:血圧上昇抑制
- フラボノール類:抗酸化、抗ガン、心疾患予防、消臭
- 複合多糖:血糖上昇抑制
- ミネラル類
・『不溶性成分70~80%』
- 食物繊維
- タンパク質
- 脂質
- クロロフィル:消臭効果
- ビタミンE:抗ガン、抗糖尿、血行促進、白内障予防、免疫機能改善
- βカロテン:免疫機能増強、ビタミンA生成源
- ミネラル類
- 香気成分:アロマテラピー効果
参考
お茶に含まれるより詳細な成分については、全国茶生産団体連合会・全国茶主産府県農協連連絡協議会のサイトをご覧くださいな。
参考
https://www.zennoh.or.jp/bu/nousan/tea/index.htm
緑茶の効果

緑茶の健康に対する効果についてはさまざまなものがあり、いろんな研究が存在しています。
例えば、緑茶の効果としては以下のようなものが確認されているとのことです。
- がん抑制に関わるもの
- 脳の機能維持、増強に関するもの
- 脳血管障害の予防に関するもの
- アレルギー緩和に関するもの
- 糖尿病予防に関するもの
- 生活習慣病予防に関するもの
- C型肝炎に対する効果
- 冷え性への応用可能性
以上の効果の詳細については以下からどうぞ。
参考
http://www.o-cha.net/kounou/kounou.html#01
また、栄養精神学の分野において緑茶には「うつ病リスクを低減させる効果がある」といわれています。
国立精神・神経医療研究センター病院の功刀(くぬぎ)浩医師(神経研究所疾病研究第三部部長)によると、緑茶にはうつ病リスクを低減させる効果があるそうです。
東北地方の70歳以上の人を対象にした調査では、緑茶を1日4杯以上飲む群は1杯以下の群に比べてうつ病リスクが半分程度であったといいます。
そして、功刀医師らのアンケート調査でも、うつ病患者は健康な人に比べると緑茶摂取量が少なかったそうですね。
緑茶がうつ病予防に効果がある理由について、同氏は「テアニンやカテキンによる薬効」によるものではないかと述べています。
なんでも、テアニンにはリラックス効果がありその摂取により神経細胞の伝達が調整され、カテキンには抗酸化効果で神経細胞と脳を守り、うつ病との関連が示唆されている脂質異常や血糖値の上昇を防ぐ効果があるからだそうです。
また、緑茶に含まれる栄養素である葉酸にも抑うつ症状の予防効果があるといいます。
テアニンの高精神作用については例えば以下みたいな論文もあるようです。
以下論文ではテアニンが統合失調症やうつ病に効果があるとの示唆がなされていますね。
参考
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsbpjjpp/27/4/27_177/_pdf
どうやら、テアニンはストレス軽減等に効果があるようですね。
また、国立国際医療研究センター疫学・予防研究科の南里明子さんらの研究によると、21~67歳の男女約530人の血液中の葉酸濃度と抑うつとの関連を調べると、男性の葉酸濃度が高い群は低い群に比べ抑うつ症状のある人が少なかったといいます。
さらに、3年後に同じ対象者を調べるとベースライン時の葉酸の血中濃度が、高い群ではうつ症状が起こりにくかったそうです。
参考
https://dot.asahi.com/wa/2016072100271.html?page=1
こんな風に体にいい緑茶ではありますが、一日に10杯くらいを限度にしておいた方がいいようですね。
ま、過ぎたるは何とやらです。
気を付けましょう。
参考
緑茶の美味しい入れ方

さて、緑茶がどれだけ心身の健康に良い飲み物であるかはよくわかっていただけたかと思います。
ですが、いくら体によいとしてもせっかくならできる限り美味しくいただきたいものです。
なので、お茶の美味しい入れかたについてもご紹介してみようかと思います。
まずは、お茶の葉とお湯の量、そしてお湯の温度についての確認です。
以下に2~3人分の標準量の場合の目安を示しておきます。
- お湯の温度 :70~80度(横ゆれして湯気が上がるくらい)
- お湯の量:180cc (1人当り60cc× 3人分)
- 浸出時間:ふたをして約1分ほど
そして、お茶の入れ方については以下のような手順でやるといいそうです。
- 1、お湯をまず人数分の湯のみに注ぐ(お湯を冷ますため、かつお湯の分量を量る事が出来るため)
- 2、急須に茶葉を入れる(茶葉の量は1人当り60ccで約2g)
- 3、あらかじめ注いでおいた湯のみのお湯をゆっくり急須に注ぎ、その後約1分ほどお茶の葉が開くまで静かに待つ
- 4、約1分ほど経過してお茶の葉が開いたら、自分の好きな濃さに合わせて、急須を3~5回まわして湯のみに均等につぎ分ける
- 5、つぎ始めは薄く後になるほど濃くなるので、お茶の濃さが平均的になるよう注ぎまわす(つぎ始めは薄く後になるほど濃くなるため)
- 6、注ぐときには急須に残らないよう必ず最後の一滴までしぼるように注ぎきる(2煎、3煎まで美味しくのむため)
参考
http://www.fukumotoen.co.jp/fukamushi/irekata.html
また、おいしいお茶をのみたいのなら「水にも注意を払うべき」でしょう。
そう、「良い水が必要」なんですね。
「いい水」と聞いて別にスーパーに水を買いに走る必要はありません。
水道水でオッケーです。
なぜなら、ここでいう「良い水」とは浄水器を通した水道水のことだから。
ただ、浄水器を持っていない人もいるとおもうので、その場合は次善の策をとります。
次善の策は水道水を一晩くみ置いてその上澄みを使う、ないし一度完全に沸騰させた後、更に5分以上煮沸させるという方法です
こうすることで、水道水のカルキ臭さがなくなります。
あと、お茶を美味しくいれるコツとして以下に注意しておくとなおいいですね。
- お湯は必ず一度完全に沸騰させる
- お茶を入れる際にポット等から直接急須にお湯を入れず、湯呑みや湯冷まし等でお湯を冷ましてから急須に入れる
- 茶葉は多めに使用し、最後の一滴まで注ぎ切るようにする(2煎、3煎まで香味が残る)
これらの手順や要点を「厳守せなあかん!」というわけではなく、あくまで参考として素敵なお茶ライフを満喫してみてください。
あと、個人的なおすすめですが、煎茶堂東京の透明急須はおしゃれだし割れにくいので凄くすきですね。
インテリアにもなるのでとっても重宝するんですよ、これ。
わたしのお気に入りの急須だったりします。
しかも、煎茶堂東京のお茶はすごくおいしいんですよねえ、ま、高いっちゃ高いんだけどね(笑)。
わたし、頻繁には飲めなくてもチャンスがあるたびに飲んでおります。
お茶で心も気分もかる~くなりましょう。
おすすめの緑茶

はい、では最後に個人的に「お!これうまくね?」とリアルガチで思った「ヤバいよヤバいよ」なお茶を紹介してみようかなって思いやす!
ちなみに、わたしはお茶の場合は紅茶と違ってそこまで特定の種類にこだわることなく幅広く飲んでいます。
では、どうぞ!
・伊藤園 おーいお茶 抹茶入りさらさら緑茶
伊藤園の煎茶です。
とてもリーズナブルなので日常使いにはとても便利ですね。
わたしは紅茶をはじめとしたお茶類を一日にかなりの量を飲むので、こういうリーズナブルなものがあると助かります。
それに安くても個人的に味は割といいと思うんですね。
スッキリして癖がないので飲みやすいです。
・上辻園 宇治玉露
こちらも玉露にしてはリーズナブルです。
煎茶に比べて苦みがなく、まろやかでコクがあるので苦みの苦手な人にはお勧めですね。
・大井川茶園 茶工場のまかない 宇治抹茶入玄米茶
玄米茶は上記では紹介しませんでしたが、玄米茶は香ばしいのでお茶に香ばしさを求める人にはお勧めです。
実際、玄米茶の香ばしさは心落ち着くんですよねえ。
なお、玄米茶にはカフェインの含有量がすくないので、カフェインの苦手な人にとってもおすすめです。
・煎茶堂東京のお茶
煎茶堂東京の煎茶はどれをとってもおいしくて大好きなのですが、今回は個人的に特に好きな4つを紹介してみようかと思います。
煎茶堂東京のサイトに行くとわかりますが、商品一覧で商品画像にカーソルを合わせるとお茶の味わいがチャートで表示されるんです。
味は以下の項目により表示されています。
- 甘味
- 牧草
- 大地
- 芳香
- 花
- 果実味
- 渋み
- 焙煎香
- コク
- 旨味
- 海苔
- 穀物
なので、自分がどういう味のお茶が好きかを事前に知っておくと自分に合ったお茶が選べます。
ちなみにわたしは渋みが好きではないのもあり、選ぶ基準としては「渋みの項目低く、かつ甘味やコク、芳香、旨味の項目が高いお茶を選ぶ」というものを採用しています。
それに煎茶堂東京はとっても容器がオシャレだったり(特にギフト缶)いろんな意味でセンスがいいので、オシャレさを重視してしまう自分としてはこれ以上ないくらいに好きなんですねえ。
やっぱ、ダサい容器とかってさ、、、あんま美味しそうじゃないじゃん、、、(偏見)。
以下のお茶は上述のわたしの基準で選んだものです。
個人的にではあれど一度飲んだら、猛烈にまた飲みたくなる、、、そんな中毒性が以下のお茶にはあるとわたしは確信してますからねえ、要注意だ!
- 煎茶同東京 さわみずか
- 煎茶同東京 うじみどり
- 煎茶同東京 香駿
- 煎茶同東京 やぶきたやめ
おわりに

この記事では「緑茶はメンタルにいいし、ウツ病予防になるかもしれない」と題しておおくりしました。
緑茶には多くの栄養素が含まれており、とても体にいいといえます。
そして、その効果も多種多様です。
その効果の中でもわたしが特に注目に値すると思うのが、うつ病の予防に寄与するというメンタルの健全化に資するもの。
日ごろから習慣的にお茶を飲んで、メンタルの健全化に励みましょう。
では、おちゃっちゃーん。
参考記事等