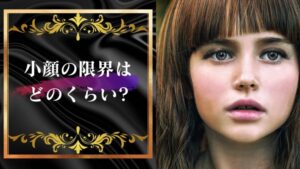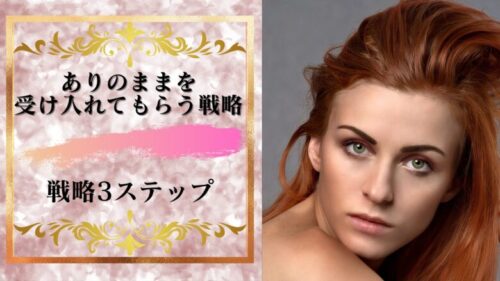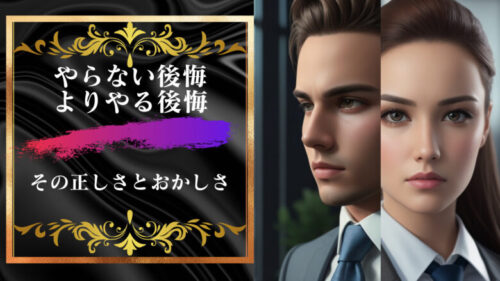「なんだか、自分は注意力が結構足りないって文句を言われるんだよな。でも、そんなにわたしの注意力が不足してるとは思わないけどなあ。、、、まあ、確かに突然起こった緊急事態には動揺して取り乱しまくるけどな。ところで、注意って一体どんな現象なん?少し気になってきた、、、」
ふむ、確かに注意ってどんな現象かよく知らんよね、、、、。
てか、みんな「あー、あれね」みたいな感じで深く考えんよね。
ま、考えるきっかけがないっていったほうが正しいけどな、多分。
オニギリス!
脱マンネリストのオニギリです!
今回もよろしゅう!!
今回は「注意って一体どんな現象なのか?ちょいと考えてみよう。「空間的注意」」という話題です。
今回は以下のような方に向けておおくりします。
- 注意ってどんな現象か気になっている人
- 注意力をあげるために何かしたいと思っている人
- 話のネタを探している人
わたしたちは日常的に「注意」という言葉を使っていますが、注意というものが具体的に一体「どんな現象か」考えたことってあるでしょうか?
多分、そんなこと考える機会ないかと思います。
てか、きっかけがそもそもないですよね?
そんな注意というものについて今回はすこーし深く突っ込んでみたいと思います。
注意ってどんな現象なんでしょう?
では、ゆるりとおおくりします。
目次
注意っていったいどんな現象なん?
さて、わたしたちは日常で「注意する」とか「注意散漫」、「注意不足」みたいに「注意」という言葉を使っていますが、そもそも注意っていったいどんな現象なんでしょうか?
注意とは端的に言うなら、
「外的刺激の一部を優先的に処理すること」
です。
人間は全ての情報を等しく処理しているわけではないんですね。
てか、そんなことしたら処理能力の範囲を超えて頭がエンストしてしまいます。
なので、人間の脳は
「ふむ、これはいらない情報だよ。こっちは大事だね」
みたいに常に流れ込んでくる外界からの情報を仕分けして優先順位をつけているんです。
そのために、以前当ブログで扱った「カクテルパーティー効果」なんてものが起こったりするんですね。
カクテルパーティー効果について詳しくは以下からどうぞ。
注意とは文字通り「意識を注ぐ」ことなわけですよ、ある特定のものにね。
で、一般に言われる「注意」というものをより学術的に言うならば「空間的注意」という事になります。
人間の感覚には聴覚や視覚、触覚等々いろいろあるわけですが、注意はそのそれぞれの感覚の種類(モダリティともいう。例:聴覚)や属性(固有の性質や特徴のこと。例:性別、年齢、人種等)に対して能動的、ないし受動的に向けられるんですね。
空間的注意とは「ある特定のものに向けられるもののこと」を指します。
例えば、救急車のサイレンが聞こえてきたらその音が気になって他のことが上の空になるとか、ジャイアンのかっ飛ばしたボールが急に視界に入ってきたので反射的に目がいく、ジャズのliveにいってベースラインに意識を向けて聞き入るなんてものも空間的注意ですね。
注意の種類と復帰抑制
感覚的に当たり前のことですが、注意をある位置や色に向けるとその属性を持っている対象に素早く気がついたりその速度が上昇します。
例えば、「この中から青色を選んでください」と指示されて50色の円が映っている写真を見せられたとしましょう。
そうすると、スムーズに「青色の円」を選択できるはず。
それは事前指示によって、「青色」という属性に注意が向けられているからです。
で、空間的注意には以下のような種類があるんですねえ。
・内発的注意
意図的に制御する注意のことを内発的注意(トップダウン注意や目的指向性注意とも言われる)。
・外発的注意
フラッシュのような顕著な刺激によって強制的に向けられる注意のこと。
例えば、救急車のサイレンや防災訓練用のサイレンが突然なりだしたりすると反射的にそっちに意識がいく。
参考
https://bsd.neuroinf.jp/wiki/%E7%A9%BA%E9%96%93%E7%9A%84%E6%B3%A8%E6%84%8F
そして注意が向けられた場所においては空間解像度やコントラスト感度が向上しますが、そのあとに注意が他に移動した場合、最初に注意された場所や物体に対して再び注意を向け直すことが困難になるといいます(2秒程度)。
※コントラスト感度とは空間正弦波パターンの明暗の差がないようにした場合に、縞模様が判別できる限界のこと。
正弦波パターンについて詳しくは以下。
このように注意を向けにくくなることを注意の復帰抑制といいます。
ここでの説明はかなーり大雑把で厳密性をかくものなので、より詳細かつ厳密に知りたいって人は以下を参照してくださいな。
参考
https://kotobank.jp/word/%E6%B3%A8%E6%84%8F-97000
注意力を高める方法って何かあるかね?
まあ、ここまでで終わってもいいんですが、この記事を読んでいる人の中には「注意力を高めたい!」と思っている方もいると思うので注意力を高める方法についても実際にわたしが体験して有効な気がすると思うものを提示させてもらおうかと思う次第。
注意力を高めるということは集中力を鍛えることではなく、「情報の取捨選択を鍛える事」です。
この「情報の取捨選択」を鍛えるためには、「何かの絵を模写したり自然物をスケッチする」のがいいでしょう。
わたしもいつもではないですが、たまに気が向いた時にスケッチとか何かの絵を模写したりみたいなことを能動的にやってみたりしていますが、体感で少しは注意深くなっている?気がしています。
実は、このようにスケッチを通して注意力を養うという方法は昔から研究者たちにより実践されてきた「フィールドノートをつける」というものに通ずるものなんですね。
観察対象の細部について記述し、「みたまま」をスケッチするのがフィールドノートです。
わたしの場合はただ観察して模写しているだけですが、観察する際に「ここはどうなっているのか?どういう構造なのか?」なんて頭の中では思いながら模写してたりします。
スケッチする際には「これは大事であるがこれはいらない」という情報の選択をすることになりますから、注意力を鍛えるためにはうってつけの方法といえますね。
たまに「これは写真なの?」みたいに驚嘆するレベルのデッサンをする人がいますが、そんな人たちは対象物の細部を観察して「これはいる、これはいらない」と的確に情報を取捨選択して写真と見まごう作品を作っているわけです。
彼らは注意力の達人なのかもしれませんねえ。
絵をかくのも気分転換になるので、何か題材を見つけてデッサンしてみるのもいいですね。
お試しあれ。
おわりに
この記事は「注意って一体どんな現象なのか?ちょいと考えてみよう。「心理学」」と題しておおくりしました。
注意って「そもそもどんな現象なんだろうか?」なんて中々日常で疑問に思うことはないですね。
でも、注意について少し深く突っ込んでみると、人間の認知機能の面白さというか興味深さ?みたいなものを感じることになると思います。
ほんと、人間の認知機能って不思議だし興味深いっす。
では!
参考
https://bsd.neuroinf.jp/wiki/%E7%A9%BA%E9%96%93%E7%9A%84%E6%B3%A8%E6%84%8F
https://www.lifehacker.jp/2013/06/130630attention.html
https://kotobank.jp/word/%E6%B3%A8%E6%84%8F-97000
参考記事等
『仮現運動』動いていないのに動いているように見えてしまう不思議
『プルキンエ現象』日が暮れると青いものは明るく見え赤いものは暗く見える?
心理学でいう、トップダウン処理とボトムアップ処理っていったい何?