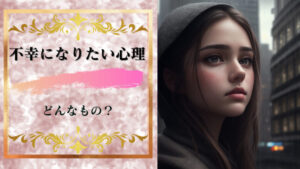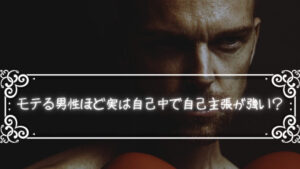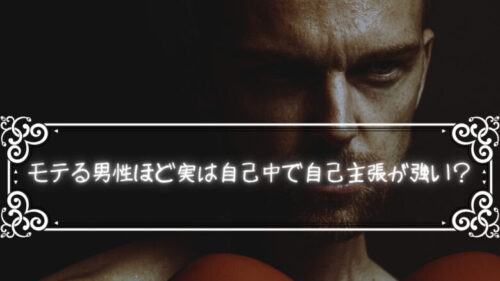オニギリス!!
脱マンネリストのおにぎりです!今回もよろしゅう!!
今回はよく話題になる「コミュ障」についてです!!
結論から言うと、コミュ障は「言いたいことも言えずに…」というタイプだけではなかったんですねえ。
「自分うまくコミュニケーションとれてないなあ…」
なんて心当たりあるひとに解決策を提案いたします!
では、詳しく見ていくとしますか?
ちなみに、職場に理不尽な怒りをぶつけてくる上司や先輩、同僚等がいるという人は、「ストレスコミュニケーション対策」の記事が参考になるでしょう。
Here we go!!
目次
1、コミュ障とはコミュニケーション障害の略称

現代では、みんな当り前のように
「コミュ障コミュ障コミュ障コミュ障コミュ障…」
と念仏のようにそこかしこでつぶやいていますね。

「いや、さすがにそんなにひどくないだろ」
あー、たしかに盛りすぎました。すんまそん。
そんなコミュ障はご存じのとおり「コミュニケーション障害」の略称です。
ただし、ここで注意したいのは「障害」とついてはいても医学上の障害ではない点です。
では、コミュ障の定義をニコニコ大百科さんに聞いてみますか?
ニコニコ大百科さんによると
コミュ障(こみゅしょう)とは、コミュニケーション障害の略である。実際に定義される障害としてのコミュニケーション障害とは大きく異なり、他人との他愛もない雑談が非常に苦痛であったり、とても苦手な人のことを指して言われる。
https://dic.nicovideo.jp/a/%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%A5%E9%9A%9C
とあります。
簡単に言うなら、方向性が定まらない会話に苦痛を感じるひとでしょうか。
そして、よくある勘違いにいわゆる「コミュ障」と「人見知り」を同一視することがあります。
では、こんどはWIKIPEDIAさんのお力をかりましょう!
WIKIPEDIAさんによると
人見知り(ひとみしり、英: Shyness)とは、従来は子供が知らない人を見て、恥ずかしがったり嫌ったりすることである。大人の場合は「内気」・「照れ屋」・「はにかみ屋」・「恥ずかしがり屋」の言葉をあてるのが標準的である。社会心理学では、社会的場面における上記のような行動傾向をシャイネスという[1]。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%BA%E8%A6%8B%E7%9F%A5%E3%82%8A
とのこと。
さて、何か同じことをいっているようにも思えますが、実際には人見知りとコミュ障は別物です。
なぜなら、人見知りは社会心理学でいうところのシャイネス。
シャイネスとは社会心理学者のリアリーの言をかりるなら
「他者から評価されると予想することが、あるいは実際に評価されることがもたらす対人不安と対人抑制という特徴をもつ感情-行動症候群」のことです。
シャイネスの根底にあるのは対人不安と対人抑制なんです。
要するに、ひとと会うと不安になり自分の素直な気持ちが出せなくなること。
しかし、いわゆるコミュ障には素直すぎて逆に意思疎通が取れない人がいるのです!
ですから、人見知りはコミュ障の一部であり全体ではないといえそうです。
では、この違いを念頭におきつつコミュ障を種類別に見ていきましょう。
2、いわゆるコミュ障の分類

・一般的なイメージのコミュ障
はい、このタイプこそがコミュ障の代名詞的タイプといえます。

「これパパが買ってくれたラジコンだぜ。いいだろ~」

「あ、そうなんだ…」
まあ、若干上のひとがドラえもんのスネ夫氏っぽいのはおいといて、こんなふうに言葉に詰まって次の言葉がスムーズに出てこない人達です。
このタイプは前述の人見知りとほぼ同じ類型と考えてよさそうです。
・よくしゃべるコミュ障
ここ
はい、正直言ってこのタイプが一番厄介です。本人がコミュ障である自覚が無いにも関わらず、気が付いたら「あれ?おれ嫌われてね?」となっているタイプです。
重症化すると嫌われていることにすら気づいていないことも…。
なにより関わるひと達がいちじるしく疲弊するのがこのタイプの特徴といえます。

「こないだグアムにいってyo。おじさんがもってるクルーザーにのったんだけどyo。サーフィンも…」

「はあ…(いつまでしゃべってんねん!しばくぞタコ!)」
このタイプは自分が話したいことを相手の都合お構いなしに話し続けます。まさに地獄のマシンガントーク。会話は双方向でないと成り立たないので、このタイプは会話を放棄しているともいえそうです。
てか、上だれやねん。
3、コミュ障の種類別改善法

では、以下順次タイプごとに対策を講じていきましょう。
・1、しゃべれないタイプ
・小さな成功体験をつむ
いわゆる一般的なコミュ障のひと達は、さきほどのシャイネスの定義からうかがい知れるように他人からの評価をおそれます。
つまり、コミュ障の原因は自分に自信がないことです。
ですから、自身を付けて自己肯定感を高めていく必要があるんです。
そのためには何と言っても成功体験をつむこと。ただし、無理のない範囲で。
まずは行動から変えてみましょう。例えば、コンビニにいったら店員の人にあいさつするとかそんなことでいいんです。そして、すこしでも以前よりあいさつしようとした、できたなら素直に
「わたしもやればできるじゃん!」
大いに自分をほめてあげてください。
それを続けているうちに自信がついてくるはずです。
・マインドスクリプトを駆使する

「マインドスクリプト?」
早速変な言葉が出てきましたね。マインドスクリプト。
これなんざんしょ?
マインドスクリプトとは「自分の気持ちを心に表明すること」。
短く単純で前向きな言葉を相手に会う前に心の中でとなえ、相手との会話をしている時もそれを反復するというものです。
端的に言って自己暗示の一種です。
たとえば、相手に会う前に
「わたしはあなたが好きだ。そして、あなたもわたしを好きだ。だから、この会話はきっとうまくいく!」
このような前向きな言葉を心の中で唱えてみましょう。
きっとこれだけでも幾分心が落ち着くと思います。
・発想をかえてみる
発想を変える。つまり、心理学でいうところのリフレーミングの応用です。
リフレーミングについて詳しく知りたい方は以下関連記事へどうぞ。
おそらく、「ひとと話すだけで心臓がバクバクするんじゃー!!」なんて心の中心で叫んでるひとも多いんじゃないかと思うんです。
そんなひとはきっと「落ち着け!落ち着け!」と必死になるあまり、ますますあせるという悪循環にハマっていたりします。
だから、発想自体かえちゃいましょう。
もし、心臓がバクバクするなら…
「体が重要なことのために準備をしろといっている。なにせ、これからわたしは人と話をするのだから」みたいに緊張を抑えつけることを頑張るのではなく、感じる緊張感の意味を再解釈してしまいましょう。
この方法はきっと役に立つと思います。
・2、しゃべりすぎるタイプ
・自分の心の中のひとりごとをやめる
さて、しゃべりすぎるタイプのひとがなんでコミュニケーションに失敗するかというと、その原因は間違いなく
「人の話を聞いていないから、または聞けないから」
ほぼこれに尽きるんじゃないかと思います。ですから、正直な話、根本解決をしようとすると心理カウンセラーが用いる「傾聴」スキルが必要になってきます。
しかし、このスキルをいきなり修得しようとしても無理があるのでちょっとした対処法を提案させてもらいたいと思います。
それは「自分の心の中のひとりごとをやめる」ことです。

「ん??何それ??」
はい、そうですね。
いきなりこんなことを言われても何が何やらですね。
端的にいえば、相手に対する自分の思い込みを捨てようということです。
わたし達の多くは相手の話を聞きながら

「あー、このひとが言っているのはこの話題か。だったらきっと結論はこうだな。」
みたいに相手の話を最後まで聞いてもいないのに結論を先回りして決めつけているんです。
これをすると人の話を聞かなくなります。
結論が分かっている話をきくなんて時間の無駄と考えるひとは多いでしょうからね。
そうなったら、ひとの話をさえぎる、ひとの話をはなから否定することになります。
良質なコミュニケーションが取れるはずなんてありません。
だから、ひとが話していたらこの独り言はストップ。最後までじれったくとも話を聞きましょう。
慣れればそんなに苦でなくなるはずです。
・謙虚になる

「へ?どゆこと?」
はい、説明します。しゃべりすぎる人の全員が全員ではないにせよ、一方的にはなすひとは自信がありすぎるきらいがあります。
言ってしまえば傲慢です。
こんなひと達は得てして自分が話し上手だと思っていたりします。だから、ひとの話なんて当然聞きません。
だから、謙虚にならないといけないんです。
しゃべれないひとの場合とは逆にもっと「相手がどんな様子か観察する」。
この意識をぜひとも持っておいてください。
ただ、それを意識していても話し過ぎる事はあります。
もし、少し話し過ぎたとおもったら、あやまった上で相手に会話の主導権をわたせばまだ相手の嫌悪感は少なくすむと思います。
これを心掛けるだけで大分スムーズに会話が進みます。
・相手に感謝する
さきほどの謙虚になるのと感謝するのは似ているような気もしますが少しちがいます。
具体的には
「はなしを聞いてくれてありがとう」
という感謝の気持ちをもって話をしようということ。この気持ちがあればより謙虚になれる上、相手をもてなす気持ちで会話ができます。
そうです。会話とは「おもてなし」なのです!
この気持ちさえもてれば大分問題が解決できるとおもいます。
おわりに

この記事ではいわゆるコミュ障の種類とその種類と原因別の改善方法について述べました。
しつこいようですが、「会話はおもてなし」です。
どちらか一方だけが気分よく話す、これは会話というよりただの嫌がらせです。
会話は話し手と聞き手のお互いの気遣いあってこそ成立します。
だから、しゃべりすぎなひとは今までより気遣い、しゃべれないひとは今までより気を遣いすぎないことが必要です。
話し手と聞き手、この両者の気遣いの均衡こそが会話を成立させます。
「気遣いは思いという使節の派遣。相手に非礼があってはならない。緊張は当然起こるもの。緊張を感じるのは恥じる事ではない。誇るべきことだ。あなたは素晴らしい使節団を心に率いている」。
by ぐれんのオニギリ